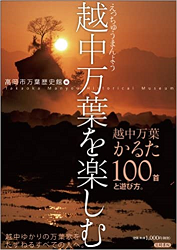まんれきブログ -
越中万葉歌を読む~越中万葉かるたの世界~
008回「雁がねは 使ひに来むと 騒くらむ」
2020年08月30日

雁は
使いとしてやって来ようと
鳴き騒いでいることでしょう。
秋風が寒くなってきたので、
その川のほとりで。
雁がねは 使ひに来(こ)むと 騒くらむ 秋風寒み その川の上(へ)に
大伴家持(巻17・三九五三)
前回連載7回の歌に続く宴の歌全十三首(「越中万葉かるた」では連載3~10回の八首を選出)の内の一首です。
「雁がね」は本来雁の鳴き声のことですが、ここでは雁そのものを指しています。秋になると日本に飛来する渡り鳥の雁は、匈奴(きようど)に捕らえられた前漢の時代の蘇武(そぶ)が、手紙を雁の足に結びつけて放ったという中国の故事(『漢書』蘇武伝)から、遠く離れた人に便りを運ぶ使いと考えられていました。
この歌では、秋風が寒いので、遠い北方の川辺では、雁が都にいる妻の使者としてやって来ようと意気込んで鳴き騒いでいるだろうと想像しています。(田中夏陽子)
高岡市万葉歴史館編
『越中万葉を楽しむ 越中万葉かるた100首と遊び方』
笠間書院・2014年刊
フルカラーA5判・128頁・定価1000円
※本文の中で引用した歌の読み下し文は、高岡市万葉歴史館編『越中万葉百科』(笠間書院)によります。